みんげい おくむら トップページ > みんげい おくむらとは > 国内展示会 > 2018年 しょうぶ学園(鹿児島) |
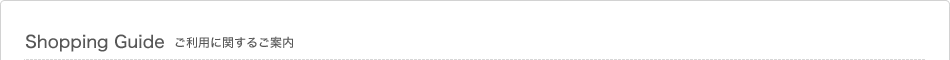
-
-
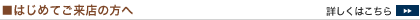
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
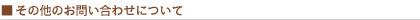
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.

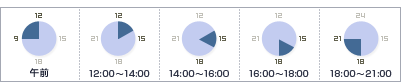
2018年しょうぶ学園(鹿児島)
日本民藝協会の民藝夏期学校が鹿児島で行われると艸茅窯の川野さんに聞いたのは、
2017年のことだった。
鹿児島は民藝協会が無いので、川野さんが引き受けていろんなことを企画されていた。
まさか自分にまで話が回ってくるとは思わずに。
民藝夏期学校をしょうぶ学園で出来たらいいと言っていた川野さんから、
しょうぶ学園に決まったこと、それからそのタイミングに合わせてそこで展示会をやりたいこと、
九州の作り手をテーマにしたいこと。
そんな話があった。
(注:しょうぶ学園は鹿児島県鹿児島市吉野の障害者支援センター)
僕もしょうぶ学園のことは知っているし、
鹿児島の友人に連れてきてもらったこともある。
(たまたま甥っ子さんが僕の大学の同級生で、卒業後も東京にいて友人だったり。)
が、施設の方々と直接知り合うような仲ではなかった。
ならば、と2018年に入ってすぐの一月に川野さんとしょうぶ学園を訪ね、
施設長の福森伸さんにお話を伺った。
(学園の敷地内で、外からの人も利用できる蕎麦屋の凡太。いつもこの看板が楽しみだ。)
福森さんはもともとこの学園の売店で民藝のうつわを販売されていたり、
民藝自体にも造詣の深い方で、
川野さんと福森さんの古くからのご縁や、今されていること、考えていること、
未来への話を聞いているだけでワクワクした。
(その後川野さんはしょうぶ学園の理事にも就任されている。)
自分にできることがあれば、
精一杯やらせてもらおう、と展示のことをいろいろ考えた。
そもそも、施設のみなさんのものづくりが無作為、無為の形であり、素晴らしい。
正直なところ今のうちの扱う作り手の人たちは、
この施設のみなさんのものづくりに逆に圧倒されるんじゃないだろうか。
そんな風に思い、
声を掛ける作り手には、いつもの仕事で、
しかしできるだけ削ぎ落としたものを用意してもらおうと思った。
そして8月。
暑い時期に展示は始まった。
冒頭の写真のように、
「九州のつくり手たちとしょうぶ学園展」という企画名になり、
民藝夏期学校のTシャツも、
学園の方のアートワークで完成(これが実に素晴らしい)。
(川野さんとしょうぶ学園の福森創さんと。)
まずこの展示に際しては、
川野さん、しょうぶ学園の担当みなさん、
そして鹿児島の野はら屋佐々木かおりさん、熊本のまゆみ窯眞弓亮司さんと奥様澄子さん。
このみなさんの協力があって展示の立ち上げができました。
そのことを深く感謝しております。
私は遠方から祈るしかなかったのですが、
いざ現場を見て、安心しました。
素晴らしい展示になりました。
まず、こちらは、
しょうぶ学園のみなさんのそばちょこ、
次はそれを指導した、艸茅窯・川野恭和さんの品。
そして、 九州のベテランの作り手、
鹿児島の吹きガラス森永豊さん、
福岡の祐工窯・阿部眞士さん(川野さんの弟弟子にあたる)。
うちの取扱い以外の方は川野さんが声をかけてくれました。
ベテラン二人の仕事。
そしてうちから、
沖縄の北窯、
松田共司工房と松田米司工房。
こちらは定番の仕事。
ガラスの太田潤さん、
小石原の太田哲三窯の太田圭さん、
この二人の兄弟にも定番の仕事をお願いしました。
続いて、
熊本のまゆみ窯。
こちらは地味な透明釉の仕事に絞って。
眞弓さんは形の取り方が素晴らしいので、
形にすっと目がいくようにん、
加飾を省いて、シンプルに。
そして眞弓さんが修行した、小代焼ふもと窯。
小代焼ふもと窯は井上尚之さん。
スリップウェアは一切無しで、小代焼の仕事のみ。
それも本人が嫌がる傘立てを、
ずっとずっと頼んで作ってもらいました。
この仕上がりは素晴らしかった。
スリップを無しにした尚之さんの現在地も良かったと思う。
大分県の小鹿田焼からは(当時)若手三人。
黒木富雄窯の黒木昌伸さんには、白。
坂本工窯の坂本創さんには、黒(鉄)。
坂本浩二窯の坂本拓磨さんには、青。
をお願いしました。
それぞれの形や手が浮き彫りになる感じ。
個人的にはワクワクしました。
そして地元鹿児島。
沖縄に学び、鹿児島を表現している、
野はら屋の佐々木かおりさん。
白化粧の仕事もする佐々木さんですが、
黒もんと呼ばれる鹿児島の黒。
今の鹿児島の黒、を。
ラストは、鹿児島の民窯、
龍門司焼より、
川原竜平さん。
龍門司焼広い仕事を出してもらいました。
また、各作り手には、
しょうぶ学園の方が書いてくれた
手書きのネームプレートが。
(これを大切に持って帰って、工房に飾ってくれている作り手さんが何名もいます。嬉しい。)
しょうぶ学園、そして川野さんの胸を借りて、
この展示となりました。
ある作り手さんが、
今の世の中でこんな地味な展示をやる人はいないんじゃないの?
と褒めてくれました。
嬉しい。
しょうぶ学園のみなさんが生み出す工芸、アートの世界に対し、
僕らが扱うものは、
どうしても作為や商売、そういったものを感じさせてしまうものが多い。
ものづくりの原点のような場所で、
自分の立ち位置を見直すきっかけとなりました。