みんげい おくむら トップページ > 民藝に関する読み物 > 2017年初冬 コーカサスの手仕事を求めて(Vol.1) > アルメニアのレース細工(Vol.2) |
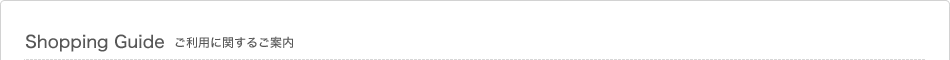
-
-
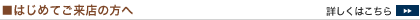
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
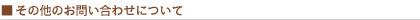
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.

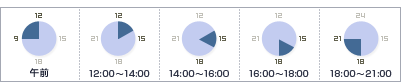
アルメニア 女性の手仕事"レース細工"。
アルメニアは美人の国だ。と言われている。
人口300万人に満たない国で、美人が多いと言われるとはいかに。
確かに、中東・アジア・ヨーロッパ、いろんな土地の良いところが集まったような顔ならばさぞ。
と想像する。
が実際のところは、思わず振り返って二度見してしまうような女性との遭遇はなかった。
多くの地域でそうであるように、かつてアルメニア美人だったのだろうなぁ、という人は見た。たくさん。
しかしどこに隠れているんだ、現役のアルメニア美人は。
ちょっと真面目な話をすると、若い人が国外に出て行ってしまうという社会問題があるそうで、
そんな社会背景が原因かもしれない。
話を本題に。
絨毯も主に女性の仕事であるが、他にも女性の手仕事がある。
レース細工だ。
アルメニアに入ったその日、僕らは小さな博物館に行った。
エレバンフォークアートミュージアムというその博物館は市街地の北の外れ。
大学がいくつかある、雰囲気の良い場所にある。
"Yerevan Folk art Museum"
Address: 64 Abovyan St, Yerevan Open from Tuesday to Sunday
From Tuesday to Saturday it’s open from 10 am to 5 pm
On Sundays from 10 am to 4 pm
正直なことを言うと、それほど期待していなかったのだが、
予想を裏切ってこれがなかなかによかった。
特に、衣装とレースの展示に関しては素晴らしかったように思う。
来館者も他におらず、実にのんびりと、しかし食い入るように閉館間際まで見させてもらった。
アルメニアに行かれる方にはぜひオススメしたい博物館。
博物館で素晴らしいものを見たから、古いものでも今のものでもいいからレース細工に出会いたいとは思った。
が、どこに行けば、誰に会えば良いのかは全く糸口がなかった。
が、願えば叶うものである。ある場所でレースを売っているおばちゃん達に出会った。
なんなら、売りながらその場で作っているのだ。
寒い日だった。
日陰で足元から冷えがくるような、そんな日も一つ一つ、レースを仕上げていく。
正直なことを言えば、こうした女性的な手仕事には造詣が深くない。
しかし、ものを見ればさすがにわかる。
人の手の仕事らしさがあるし、美しい。
装飾品のようなものは好まないので、テーブル周りのものをあるだけ譲ってもらった。
後日、調べたところやはりアルメニアのレース細工はトルコで「オヤ」と呼ばれるレース細工と類似したもので、
針と糸だけで作られる「結び」のレース細工。
その歴史は深く(紀元前2,000年からと言われる)、モチーフには絨毯と共通したものもあるそうだ。
レースの起源とも言われるそう。
ワインも起源、レースも起源。
アルメニア、深いぞ。
買い付けたのはテーブル周りのものだけなのだけど、
首に巻く付け襟のようなものも素晴らしかったし、
博物館にあった、麻(だと思う)のハンカチの縁取りに丁寧に装飾されたものも実に素晴らしかった。
精巧だが、元来売り物としてではなく家族や自分のためのものとして作られたものは民族衣装に通じる美しさがある。
レースは思わぬ収穫だったものの、実は寒い土地。
そして絨毯がある。
期待していたのはウールのニット細工だった。
ウールの手編みの靴下やベスト、ニット。
少々は見つかったものの、これ、というものには出会えなかった。
きっとどこかにあるんだろうな。これだけはちょっと残念だった。
ところで、アルメニアの女性を想う時、印象に残った2つのイメージがある。
一つは首都エレバンの地下街で見た花屋だ。
花がそれほど美しかったわけでもないし、アレンジがよかったわけでもない。
ただ、とても印象に残っている。
寒い日の夕方、地下街のそこに、花屋があった。
季節もあってか、色の少ない町だったからとても印象的だ。
もう一つは、ずっとこの旅でドライバーをお願いしていたValdanの家に招かれた時、
彼の母と奥さんの手作りの料理を腹一杯頂いて、その後にお茶を頂いて時に出された果物のコンポートだ。
これまた特別美味しかったわけではなく、どちらかというととても甘くて苦手なぐらいだったのだが、
コンポートのある食卓の絵が鮮烈に思い出される。
文章:奥村忍(みんげい おくむら) / 写真:在本彌生