みんげい おくむら トップページ > 世界の民藝 > 中国の民芸 > 中国の陶磁器 > 中国 福建省 徳化窯の磁器 > 2024年6月の徳化訪問(読み物) |
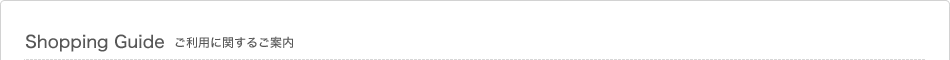
-
-
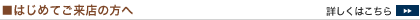
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
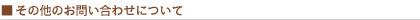
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.

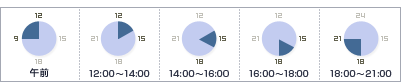
2024年6月の徳化(とっか)訪問
しとしとと降り続いた雨。
前回は2024年4月に中国福建省の徳化(とっか)を訪ねましたが、あいにくの悪天候で町の全容、
そして徳化という一大磁器産地の現在の様子が全く掴めずに終わった。
これは悔しい、と
すぐに再訪問を決め、二ヶ月後にまた渡航してしまった。
徳化は人口30万人ほどの中国で言えば非常に小さな都市になる。
感覚としては日本の地方県庁所在地のような感じだろうか。
町の中心を走る川沿いには高層マンションやビルが立ち並び、
そこを離れるとだんだん建物も低くなっていくような、そんな感じ。
町自体は比較的狭いため、
焼き物屋(個人や家族というよりは企業)は、
ビルの中にあったり、
ビルごとそれだったりする。
(建物から煙突が出ていれば、それは建物内の窯の排煙用の煙突だ。)
量産産地なので、
型物の味気ない現代的な食器や茶器、ノベルティなどを作っている会社が多いようだ。
町を歩けば、
このようにちょっとした工房を目にすることもあるし、
至る所に掲示板があり、そこに製造に関わる求人が山ほど出ているし、
オート三輪が素焼きをした食器などをどこかに運ぶ姿など、
いかにも窯場、という景色を
現代的な都市の中で見ることができるのは、
以前に訪ねた景徳鎮とは大きく違う様子である。
景徳鎮はあまりこのような都市型産地ではなく、
日本であれば瀬戸のような、
せいぜい数階建ての建物が並ぶ、そんな景色だ。
徳化という産地
徳化には街中に博物館と、世界遺産になっている窯跡がある。
どちらも興味のある人には楽しいだろう。
(窯跡から町を望む。目の前は小学校。薪窯だったころの窯具が窯跡へのアプローチに使われており、センス良し。)
古い産地だが、 明の時代にその白磁は最も美しい白を表現したとされ、
実際に明の時代のものは柔らかな乳白がかった白がたまらなく美しい。
続く清代は、よりクリアな白となり、
作られるものもシャープさを増す。
(仲良しの厦門「原色茶陶」の老板所有の徳化。餅型やその左右は明代のもの。手前の薄い茶杯は清代。)
(お茶を淹れてくれた骨董屋の老板。蓋碗の蓋は清代、ボディは民国。愛用の茶杯は清代のものだ。)
(清代末期から民国に作られた型物の豆皿。染付がのんびりしてとても良い。)
現代になると、白の表現は多様化するが、
中華民国時代、まだ薪の窯であった頃の、ややグレーがかった、
少々のんびりとした雑器時代のものは、
量産ながらシンプルな心地よい美しさを持つ。
(2024年現在の徳化の茶器。その中でもこれはセンスの良いもので、パンダやさまざまな中国風の染付がなされたものが主。)
この明、清、民国、この三時代のものが我々、というか、
うちのお客さんが好みそうなゾーンである。
窯跡には、ちょっとした展示があり、
自動車以前の時代の、
茶葉古道ならぬ、磁器古道のような展示があった。
かつては天秤棒の左右に大きな竹籠。
その中に磁器を入れ、
持ち運んだのである。
数キロ、数十キロ、
もちろん人手だけでなく、動物の力も借りたのではあるが、
器の重さは今もかつても変わらない。
生活道具、なんて簡単に言うけれど、
パッと買える時代から一気にその頃の時代にタイムスリップできる良い展示だった。
そのことを小鹿田で話したら、
かつては小鹿田も山を越えて大分の東海岸まで運ばれ、
そこから四国にうつわが船で運ばれていたという。
いつか四国でその頃の小鹿田焼と遭遇してみたいものである。
(夕暮れの徳化。川沿いには思い思いの夕暮れを楽しむ人の姿。どこの中国の都市にも見られる風景だ。)
横道に逸れたけれど、
うちではこれからも定期的に徳化のうつわの入荷がある。
その度に誰かがこのページを参考にし、
少し徳化について思いを馳せてくれれば何より。
徳化のうつわの商品一覧はこちらから。