みんげい おくむら トップページ > 民藝に関する読み物 > アジアの民藝を巡る旅 > 2013年 インドネシア スンバ島 絣の旅 > 2013年 インドネシア スンバ島 絣の旅 その3 |
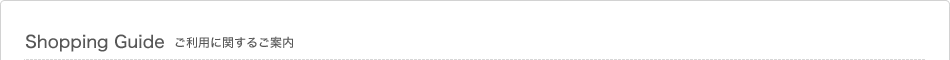
-
-
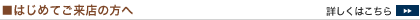
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
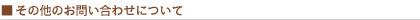
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.
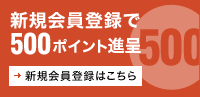


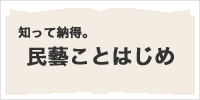

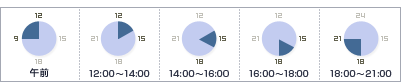
2013年 インドネシア スンバ島 絣の旅 その3
スンバ島到着から3日目、いよいよイカット(絣)が織られている村へ向かいます。
事前の情報収集では、イカットが織られている村はいくつもあるが、
昔からの織り方(手紡ぎ手織りの綿に天然染め、地機)を今も続けている村は少なく、
出来るだけそういう織りを続けている村3カ所に的を絞り、訪問します。
インドネシア スンバ島のイカット(絣)
インドネシアは東西約5,000km、南北約2,000km。そして18,000以上の島々から(政府も正確な島の数を把握していないらしい!)
構成される国ですから、イカットも地域や島、民族によって様々に異なります。
その中でも特に「ヌサトゥンガラ」(南東の島々という意味)と呼ばれる1,000余りの島からなる諸島は、
経絣(たてがすり)と呼ばれる、縦糸だけで絣模様を出した織物(つまり緯糸(よこいと)は無地で、糸に染めを施し、
織機に張った段階で模様がわかるもの。)が伝統的に織られています。
※縦糸が準備された状態。この状態で柄が全てわかるのが経絣の特徴です。
この地域のイカットは世界中に(特にオランダからヨーロッパ各地に)コレクターが多く、珍重されている織物です。
イカットはそもそも何のために使われてきたのか、と言えば、
衣服として、冠婚葬祭の儀礼や結納、葬儀の副葬品としてなどかなり幅が広い用途で使われてきています。
そんな中でスンバ島のイカットは伝統的には精霊信仰に基づくモチーフが多く、
また、この地域の中でも特に美しいものが多く、世界中から注目されています。
オランダ植民地化の後はバリのオランダ人の注文で十字架などキリスト教のモチーフや欧風のモチーフが
組み込まれたものも見られます。
スンバ島のイカット(絣)の今
2013年現在、スンバ島で手紡ぎの糸を使ってイカットを作っている村はとても少ないことがわかりました。
無いことはないのですが、それはとても高く、我々日本人でも簡単に手を出す事ができないような金額のものです。
多くの村は、機械織りの糸を用い、それに染めを施していますが、
いくつかの村では化学染料を使い、伝統的ではないモノを作り、バリなどへお土産用として出荷しています。
また町中の市場やホテルに押し掛けてくる物売りなどは、こうした村から安く仕入れたり、
信用のできないルートで仕入れをしていることがわかりましたので当店ではこうした仕入れは一切せず、
直接目の前で、染め、織りをしている3カ所の村から仕入れています。
写真は、村々の風景。こうした伝統的な織物の村は建物や祭礼など、
比較的伝統的な文化が色濃く残っている。
次のページではインドネシアスンバ島のイカットの作り方をご紹介します。