みんげい おくむら トップページ > 民藝に関する読み物 > アジアの民藝を巡る旅 > 2013年 インドネシア スンバ島 絣の旅 > 2013年 インドネシア スンバ島 絣の旅 その4 |
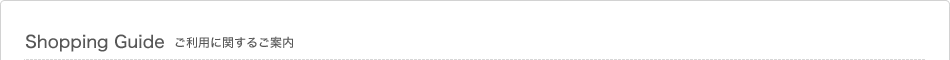
-
-
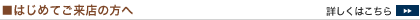
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
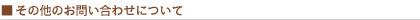
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.
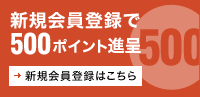


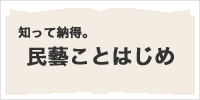

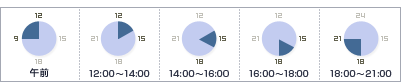
2013年 インドネシア スンバ島 絣の旅 その4 イカットが出来るまで
スンバ島で三カ所の村を回り、イカット作りを見ましたが、
イカットの基本的な作り方は以下のようなものです。
イカットの糸の紡ぎ、括り。
スンバ島のイカットで使われるのは綿です。元々は綿花を紡いで、一本の糸にする手紡ぎでしたが、
現在ではほとんどの村で機械織の糸を用いています。
ごくわずかな手紡ぎの糸は高価で、機械織の糸を用いて作られたイカットとはかなり値段に違いが出ます。
写真左:機械織の糸、写真中:括りのため糸を整える、写真右:手紡ぎの糸で作られたイカット。独特の風合い。
そして絣の絣たる大事な工程が「括り」(くくり)。どんな模様を描くかを想像し(現在では下絵があったり)
絵柄を括っていきます。かつてはこれが全てフリーハンドで、同じものは2つと無かったのですが、
現在は海外からの注文などがあるため、下絵を残し、同じものが再生産できるようにしているのがほとんど。
また、括りには伝統的には天然の葉や草が使われていますが、今はビニールテープを活用する作り手も多いです。
個人的にはやはり天然のものの方が見栄えが良いように思いますが、
ビニールテープの方が括りの精度は高いのかもしれません。
前ページで説明しましたが、スンバ島のイカットは経絣ですので、括りができた時点で布の全体像が見えてきます。
イカットの糸の染め。
括られた糸を染めていきます。
スンバ島は藍染めとその他天然染料による染めが主流で、
植物の根や葉などを使って、赤、黄色などの柔らかな色を出していきます。
根を砕いたりする工程もどこかのんびりで、穏やかな風景です。
写真下段はある村の藍染め名人の母娘。藍染めをする女性は爪まで真っ青。写真を恥ずかしがりますが素敵な手です。
染めが終わった糸は干され、その後括りを解き、織りの準備に入ります。
織る時に模様がズレては台無しですから、そこに気をつけながら整えていきます。
地味ですが、根気のいる、そして仕上りに影響する大事な作業でもあります。
イカットの織り。
インドネシア、スンバ島のイカットの織りの特徴は、絣自体が経絣で、横糸が無地であること。
また地機(じばた)と言われる(別名:腰機(こしばた))原始的な手織りでゆっくりと織られていきます。
このようにして織られるスンバ島のイカット。
藍染めのイカットは特に染めから時間がかかるのでスンバ島の中でもやや高価なものです。
そして、そのモチーフには様々な意味が込められます。
それぞれの商品の説明として、記載しておりますのでそちらを是非ご覧下さい。