沖縄の焼物(やちむん)の歴史から現在のものづくりまで。壺屋時代、そして読谷へ場所を移し現在に至るやちむん(上焼)のストーリーです。
みんげい おくむら トップページ > 産地で選ぶ > 産地で選ぶ器(焼物) > 沖縄のやちむん(壺屋焼・読谷山焼・琉球南蛮など) > やちむんの歴史(読み物) |
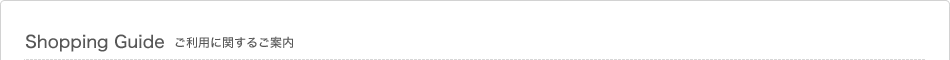
-
-
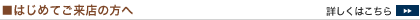
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
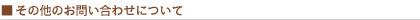
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.
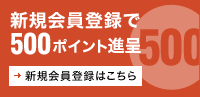


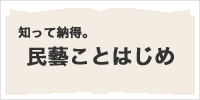

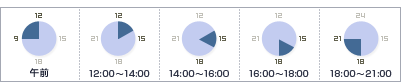
やちむんの歴史
やちむんの歴史は長く、琉球王朝が海外と盛んに交易をしていた14世紀から
16世紀のころ中国や南方諸国の陶磁器が輸入され、南蛮焼きの技術が伝えられ、
600年もの歴史があると言われています。
江戸初期、1609年に薩摩の島津藩が琉球に侵攻、薩摩藩に占領されるとともに、
交易でも様々な制約を受ける羽目になり、17世紀、琉球王朝の尚貞王が産業振興目的で、
地方に分散していた幾つもの窯場を市街の一角に固め、「やちむん」と呼ばれる焼き物街を作ったそうです。
これが壺屋焼の始まりです。
(11月下旬の沖縄。温暖な気候、豊かな土地、全てがやちむんを作る素材になります。)
民藝運動と沖縄・やちむん(明治〜昭和初期)
明治に入ると他の地域から安価な焼き物が大量に流入することになり壺屋焼は危機を迎えます。
しかし、そこに民芸運動の第一人者であった柳宗悦、浜田庄司らが来訪し、
郷土の陶工、後に県下初の人間国宝にもなった金城次郎や新垣栄三郎らを指導し、技術を研磨させました。
また、沖縄の地は民藝において重要な土地と位置づけられ、それが全国に発信されると、
民藝ブームも手伝って壺屋焼は人気を仰ぎ、廃絶を免れた。
(民藝運動や民藝についてはこちらをご覧下さい。)
壺屋焼は、本土にない鮮やかな彩色が特徴で、かつあらゆる生活まわりの器が作られていました。
柳や民藝運動家たちは、庶民の日用品でこれほどまで装飾性を兼ね揃えたものは珍しいと主張します。
(色鮮やかなやちむん。鮮やかな色を生み出す釉薬も土地の自然から作られます。)
戦後のやちむん
壺屋地区は太平洋戦争(沖縄戦)で沖縄全土が焦土と化す中、比較的軽微な被害で済み、
再興に従って、壺屋焼も徐々に勢いを取り戻します。
しかし、窯は市街地に集中しているため、今度は薪窯による黒煙の害が深刻な問題となり、
1970年代、那覇市は公害対策のため薪による窯使用を禁止、窯場はガス窯への転換を余儀なくされ、
伝統的な技法を失った壺屋焼は岐路に立たされます。
そこに、基地返還による土地転用を模索していた読谷村が窯元の積極的な誘致を行います。
読谷村は元々、ミンサー、花織など他の伝統工芸も多く、文化奨励に積極的、
加えて読谷周辺は原料となる良質の陶土が豊富でした。
そして薪窯の設置にも柔軟に対応したことで金城次郎初め、多くの陶芸家たちが壺屋を離れ、
読谷村に集まり、陶芸村を作ります。
現在も数十件の窯元が集まっており、「読谷やちむんの里」として観光ルートにもなっています。
一方の壺屋地区もガス窯で焼く窯元や、県内各地の焼物を扱う小売店などで賑わっており、
読谷と壺屋が今でも沖縄の焼物を支える2大エリアとなっています。
(毎年12月の読谷村の陶器市の風景から。)
また、現在ではその二カ所に限らず、工房・個人作家などが県内(本島のみならず)点在し、
やちむんさー(やちむんの作り手)の数はよくわからないくらいです。
(それくらい盛んに焼物作りがされています。)
→やちむんの商品一覧に戻る