陶器の使い始めの目止め(めどめ)の方法や目的について解説しています。民藝の器を長く楽しく使って頂くため是非ご一読ください。
みんげい おくむら トップページ > 民藝の器(陶器・磁器)を初めて使う > 陶器の目止め |
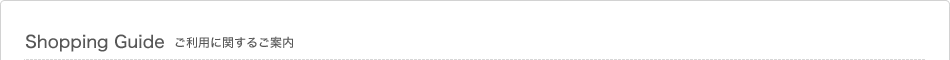
-
-
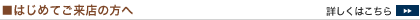
-
ご注文方法のご案内をご覧ください
-
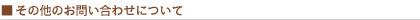
-
運営会社
株式会社 奥村商店
〒273-0005 千葉県船橋市本町6-19-8-602
お問い合わせ:orderinfo@mingei-okumura.com
電話:047-404-3960
(※買付や不在時は対応致しません。1人運営のため極力メールでの問い合わせに協力下さい。)
営業時間/平日 10:00〜18:00(土日祝祭日は定休日)
店舗責任者:奥村 忍
Copyright© 2010-2024 みんげい おくむら本店 All rights reserved.
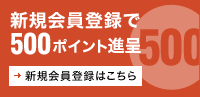


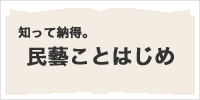

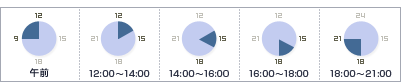
「目止め」について
陶器の使い始めには「目止め」という作業があります。
やらなくちゃいけないわけではないんです。
ただ、買ったそのままの状態をできるだけ長く使いたい方には、
こちらの作業をおすすめしております。
当店で扱う陶器や磁器は、
貫入というガラス質のヒビのようなものがあり、
そこからお醤油や油、カレーだったりキムチの汁だったり、
そんなものが入り込み、染みのような状態になったりします。
何度も洗うと状態が変わったりしますし、
それがまた経年で表情を面白くさせる、と言えますが、
中にはこれが汚らしい、と思う方もいらっしゃるのも事実です。
どちらが良いということもありませんが、
買った状態をできるだけ保ちたい方には(保証する訳ではありませんが)、
目止めの作業がおすすめ、ということです。
お茶碗など食器と、土鍋類は目止めの方法が若干違いますので、
土鍋類の目止めについてはこちらをご覧下さい。
陶器の目止めの方法
1)米のとぎ汁(なければ小麦粉を溶いた水)を器がかぶるくらい入れます。
2)20分ほど弱火で煮沸します。
3)そのまま鍋ごと冷まして、器を洗い、よく自然乾燥させます。
たったこれだけです。
目的は、粗い土の表面に米のでんぷん質をかぶせ、
その目を埋めることで汚れを染みにくくさせることです。
ただし、完璧に目が埋まるわけではないことはご理解ください。
民藝の器の中でも、重ね焼きをする器(当店では沖縄のやちむん、小鹿田焼、小代焼など)は、
その「蛇の目」の部分の吸水性が特に高いため、そこが匂いや油染みの原因になります。
気になる方は目止めをされた方が良いでしょう。
みんげい おくむら店主より
尚、私は個人的には目止めをほとんどしていません。
(土鍋は絶対にしますが。)
匂いなど、ごくたまに気になるケースもありますが、 私自身がもともと大雑把な性格ですし、
お客様より過酷な環境で器を試す、という大義名分のもと、目止めをせずに使っています。
ここは気になるか、気にならないか、器とどう付き合っていきたいか、
そんな個人差ですので、どうぞご自身の判断でお願い致します。
最後のになりますが、
当店みんげい おくむら2010年よりずっと民藝と呼ばれるものを中心として、
うつわや暮らしの道具、などなど取り扱っております。
入荷やお得なご案内がメールマガジンで流れます。
メールマガジン自体も面白いと好評です。
よろしければこちらより、
みんげい おくむら会員登録
をしておいてください。
不定期配信で、配信頻度もそこまで高くありません。
みんげい おくむらのうつわラインナップ
・北窯(松田米司 & 共司・宮城正享)
・瀬戸本業窯(水野半次郎)
・小代瑞穂窯(福田るい)
・小代焼ふもと窯(井上泰秋・尚之)
・龍門司窯(川原史郎)
・俊彦窯(清水俊彦)
・宋艸窯(竹ノ内琢)
・まゆみ窯(真弓亮司)
・太田哲三窯(太田哲三・太田圭)
・小鹿田焼(全4軒)
・瀬戸小春花窯
・三名窯(松形恭知)
・照屋窯(照屋佳信)
・古村其飯(荒焼・焼締)
・野はら屋(佐々木かおり)
・やきもの山上(宮崎匠)
・沖縄(やちむん・壺屋焼)
・瀬戸(愛知県・瀬戸焼)
・小代(熊本県・小代焼)
・丹波(兵庫県・丹波立杭焼)
・鹿児島(鹿児島県・薩摩焼)
・小石原(福岡県・小石原焼)
・小鹿田(大分県・小鹿田焼)
・伊賀(三重県・伊賀焼)
・艸茅窯(磁器・川野恭和)
・木漆工とけし(漆)
・高野 繁廣(アイヌ木工)
・奥原硝子製造所
・ガラス工房清天
・太田潤手吹きガラス工房
・再生ガラス工房てとてと
・土鍋
・すり鉢
・花瓶・花入れ
・陶器の傘立て
・睡蓮鉢
・蓋物(ふたもの)
・植木鉢
・片口
・やちむん
・スリップウェア
・茶器
・酒器
・ラーメン丼
・抹茶碗